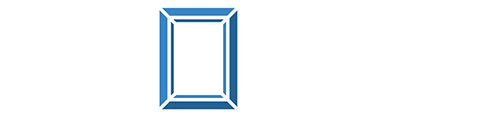会社を経営すると様々な法律知識が必要になってきます。中でも会社内部でも問題について考えるにあたって必要不可欠なのが「労働法」です。ひとくちで労働法といっても、労働法という法律は存在しません。
労働法は大きくわけると3つに分けることができます
1つめ 雇われる側と雇う側との関係を定めた法律
労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法などがこれにあたります。
2つめ 雇われる側の団体である労働組合についての法律
労働組合法、労働関係調整法などがこれにあたります。
3つめ 働きたい人と働いて欲しい人との取引についての法律
労働者派遣法、職業安定法、雇用封建法、雇用対策法などがこれにあたります。
この中でも「労働基準法」「労働関係調整法」「労働組合法」という3つの法律は、労働者と企業に関する最低限のルールを定めた法律として労働法の基本3法と呼ばれています。
ここでは、この中でもとくに企業が労働者を雇用するにあたって最低限必要なことを定めている労働基準法について解説をしていきます
労働基準法とは
労働基準法(呼称:労基法)は、企業が労働者を雇用するにあたっての最低限必要な労働条件について定めており、これを定めることによって立場が弱い労働者を保護することを目的としている法律です。
具体的にはこのあと解説をしていきますが、労働契約・賃金・労働時間・休暇・災害補償などを定めており、これによって全ての会社に対して最低限の基準を示すという役割を担っています。
本来、契約は「契約自由の原則」という原則に基づいて、当事者の自由な意思に委ねられているので企業と労働者との間の契約についても、どのような労働条件を定めても自由なはずです。しかしながらそれでは、立場の弱い労働者が企業にいいように使われてしまうかもしれないということで、この労働基準法に違反する内容の企業と労働者との間の雇用契約は、無効になります。
どの場面で適用するか
労働基準法は従業員が1名以上の企業には原則として労働基準法が適用されます。従業員の雇用形態は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等日本国内で営まれている事業に従事している労働者。
ココは抑えておくべき労働基準法
●労働条件は明示する(労基法15条)
会社が従業員と労働契約を締結する際には、「賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とされています。
また、下記5項目については、かならず書面の交付にて明示しなければなりません。
①労働契約の期間
②就業の場所・従事する業務の内容
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は、就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払い時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由も含む)
もっとも就業規則にその労働者に適用される条件が具体的に規定されている場合には、契約締結時に労働者一人一人に対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付すればよく、別途書面を交付する必要はありません。
●損害賠償を予定する契約の禁止(労基法16条)
会社は従業員が労働契約に違反する行為をしたり、あるいは何らかの不法行為を行わないようにするために、違反行為を行った場合の違約金や損害賠償を予定する契約を結ぶことは認められません。
たとえば
・無断欠勤・遅刻をした場合には○○円を支払うこと
・契約期間満了前に退職した場合には違約金を支払うこと
などを約束する場合を意味します。
もっとも、あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、実際に労働者の責任によって会社に損害が発生した場合には、損害賠償請求をすることは禁止されていません。
●解雇の制限
・病気などの休業期間とその後30日間は解雇してはならない(労基法19条)
・解雇をする場合、30日前に予告をしなければならない(労基法20)
予告をしない場合、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
これらを満たしていれば解雇ができるというわけではありません。労基法の規定はあくまでも最低限のルールであって、これらを満たしていたとしても、企業側が従業員を解雇する場合には、かなり慎重に手続きを行う必要があります。
●賃金支払いの5原則(労基法24条)
通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則ですが、毎月1回以上払い、一定期日払いの原則を一つにまとめて、賃金支払いの4原則という場合もあります。
①通貨払いの原則
賃金は通貨で払わなければなりません。ここでいう「通貨」とは、国内で強制的に通用する貨幣のことです。外国通貨等は、換金が不便であってり、価値の変動があるため、「通貨」には含まれません。
企業は一般的に従業員に対し、銀行口座へ振り込む方法で支払っていますが、これは、「通貨払いの原則」からは外れています。しかし、例外的に施行規則内で認められており、労働者の同意を得た場合のみ、銀行振り込みが可能となっています。
②直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければなりません。たとえば、労働者の親権者代理人に支払ったり、委任をうけた代理人に支払ったりすることは、この原則に反しています。もっとも、秘書や配偶者等のいわゆる使者に支払うことはこの原則に違反しないものと考えられています。
③全額払いの原則
賃金は、全額を支払わなければなりません。賃金の一部を勝手に差し引いたり、貯蓄や積み立てという名目のもと、賃金の支払いを一部留保したりすることは許されません。また、労働者が会社に借り入れがある等の場合であっても、会社が労働者に貸し付けたお金と賃金とを相殺することは認められていません。
もっとも、社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められていますし、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と労使協定を締結した場合には、賃金の一部控除が可能となります。
④毎月1回以上払いの原則
賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければなりません。臨時に支払われる賃金、賞与等については、この原則の対象ではありません。
⑤一定期間払いの原則
賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければなりません。賃金の支払日が毎月変動すると、労働者の生活が不安定になるため、それを防ぐためにこの原則が儲けられました。例えば、支払期日を「毎月第3月曜日」とするという定め方は、月により支払日がずれるのでこの原則違反ということになります。
●休業手当(労基法26条)
会社の責任で従業員が仕事を休むことになった場合、会社はその従業員に対して、休業期間中、休業手当として平均賃金の100分の60を支払い休業補償を行います。
平均賃金とは原則として、事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その対象期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で除した金額です。ただし、総額を労働日数で除した額の6割に当たる額の方が高い場合(賃金が時間額や日額、出来高で決められており、かつ労働日数が少ない場合など、)にはその額を適用します(最低保証額といいます)。
●最低賃金(労基法28条)
最低賃金とは、会社が従業員に対して最低限支払わなければならない時給のことです。最低賃金は、正社員だけではなくパートやアルバイトなど全ての従業員に適用されます。厚生労働省が毎年HP内で地域別の最低賃金額を公表しています。
もっとも労働基準法においては最低賃金について詳しく規定されておらず、最低賃金法に委ねられています。
●労働時間・休憩・休日について
<労働時間>
「1日8時間、1週40時間」を超えてはならないと定められています(労基法32条)。
この原則については一定の条件のもとで変形労働時間制やフレックスタイム制などの例外が存在しています。企業がこれらを導入する場合には、しっかりと要件を確認しておくことが必要です(働き方改革関連法にともなう労働基準法の改正いよってフレックスタイム制の清算期間が延長されています)。
また、実際に働いた時間にかかわらず、1日の所定労働時間分働いたとみなす「みなし労働時間制」として、事業場外労働制や裁量労働制なども認められています(労基法38条の2ないし38条の4)。
※裁量労働制の中の企画業務型裁量労働制は、業務の遂行手段や時間配分の決定などを労働者の裁量に委ね、成果をより重視することで業務効率や生産性の向上を図る制度で、これを取り入れる場合には、労使委員会を設置、厳格な要件を満たす必要があり、容易に長期労働を行うことができないような仕組みになっています。
<休憩>
会社は労働時間が
・6時間を超える場合には45分
・8時間を超える場合には60分以上 の
休憩を与えなければなりません(労基法34条)。
<休日>
会社は従業員に対し
・毎週1日の休日
・または4週間のうち4日以上の休日
を与えなければなりません(労基法35条)。
●時間外および休日労働、割増賃金
<36協定(労基法36条)>
会社が定める労働時間、休日の規定を超えて労働させる場合には、あらかじめ会社と労働者との間で労使協定を結んで、それを行政官庁(所轄の労働基準監督署)に届け出ることが必要となります。これが有名なサブロク協定です。
ただし36協定を締結した場合においても、
①原則として時間外時間(労働時間の規定を超えて労働した時間)が月間45時間、年間360時間を超えて労働させてはならないことになっています。
②臨時的に上記の時間を超えて労働させることは可能ですが、その場合でも、その回数が年間6回を超えてはならず、時間外+休日労働が単月100時間、2~6ヶ月の平均80時間を超えることはできません。また、時間外が年間720時間を超えることもできません。
<割増賃金(労基法37条)>
・会社は、従業員に対して時間外や休日に労働をさせた場合には、20%〜50%の間で政令が定める率以上の割増賃金を支払わなければなりません。
(2021年6月現在の*政令は時間外25%、休日35%となっています)
*労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
・時間外時間が月間60時間を超えた場合は50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
(中小企業は2023年4月から適用対象となります。)
・深夜に労働させた場合、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

<年次有給休暇(労基法39条)>
会社は、雇い入れ日から 6 ヶ月継続して勤務し、全労働日の 8 割以上出勤した 従業員に対して、10 日間の有給休暇を与えなければいけません。付与日数は勤 続年数に応じて 20 日まで増加します。ただし、週の所定労働日数が 5 日より少 なければ、付与日数は 10 日よりも少なくなることがあります。
この有給休暇は、条件を満たしたアルバイトやパート従業員にも認められます。
また、10 日以上の有休を付与した場合、そのうち 5 日は 1 年以内に必ず時季を 定めて与えなければなりません。
●適用除外(労基法41条)
労基法は原則として、全ての従業員に適用される法律です。
しかし、この適用除外に該当する者は、労働時間・休憩・休日の規制は適用されず、割増賃金の支払いが不要になります。
適用除外となるのは下記の従業員です。
・農業、水産、養蚕、畜産業に従事する者
・事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)
・機密の事務を取り扱う者
・監視または断続的労働に従事する者で、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた者
とりわけ「管理監督者」については、裁判例等でも争いになることが多くなっています。会社としてはその従業員が管理監督者に該当すれば割増賃金の支払いを免除されるので、管理監督者を主張しますが、一方従業員は割増賃金の支払いをもとめて管理監督者制を否定するという構図が多く見られます。
管理監督者は、管理職に就いているからといって簡単に認められるわけではなく、会社の中で相応の地位・権限が与えられ、経営者と一体的な立場と評価することができて初めて認められるものです。
会社としては、のちのち争いにならないように、しっかり従業員が管理監督者に該当するか否かについて認識をしておく必要があります。
●就業規則(労基法89条)
就業規則は、その会社の中で働くうえで守るべきルールを定めたものです。
常時10人以上を使用する使用者は就業規則を作成し労働基準監督署に届ける必要があります。
就業規則に記載する内容は大きく分けて以下の2点です。
1)絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
始業時刻や終業時刻、休憩時間や休日・休暇など労働条件に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
2)相対的必要記載事項(定めをする場合には記載しなければならない事項)
退職手当に関する事項
最低賃金に関する事項
安全衛生に関する事項 など
就業規則の作成や届出についての規定は労基法内にありますが、就業規則の変更については労働契約法に定められています。
●制裁規定の制限(労基法91条)
会社が従業員に減給の処分を行う場合には、以下の制限内で行わなければなりません。
・減給の一回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
・減給の総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない
●周知義務(労基法106条)
会社は、就業規則を周知する必要がありますが、その方法は下記のとおりです。
・常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
・書面を交付すること
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
働き方改革関連法
労働基準法は2019年4月の働き方改革関連法が施行されたことによって、一部改正が行われています。
これによって時間外労働の上限規制が設けられたり、年次有給休暇のうち年5日は使用者が取得時期を指定して、従業員が休暇を取りやすくなるような工夫がなされました。また企業はタイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録等を用いて労働時間の客観的把握を行い、従業員の健康管理に注意を払う必要も生まれました。
さらには同一労働同一賃金、月60時間を超える残業に対する割増賃金率引き上げ等も決まり、企業としては、しっかりと労働基準法の変化を認識し、対応することが必要とされています。
労働基準法違反
労働基準法は、労働条件の最低基準です。
この法律に違反した場合には、無効になるだけではなく、会社は労働基準監督署による立ち入り調査や指導勧告を受けることになります。
態様が悪質な場合には、書類送検されて刑事罰の対象になることもあります。
この場合、刑事罰を受けるのは「使用者」ですが、ここでいる使用者とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」(労基法10条)とされています。
したがって、経営者と管理者のみならず、「その事業の」実質的な業務権限を持ち、当該業務における「労働者」の指揮監督を行う者すべてが使用者として罰則の対象となります。
厚生労働省の発表によれば平成31年4月から令和2年3月までの間に行われた監督指導は、全国で32,981事業場、そのうち違法な時間外労働があったものが15,593事業場、賃金不払残業が2,55事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施だったものが6,419事業場となっています。 (参照https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000667303.pdf)
労働基準法違反の代表例
1)社会的な身分や性別による差別(労基法3条、5条、119条)
会社は従業員を社会的な身分や性別によって賃金、労働時間その他の労働条件について差別的な取り扱いをすることは禁じられています。これに違反した場合には、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。
2)意に反する強制労働(労基法5条、117条)
会社は従業員の意思に反して労働を強制させることができません。これに違反した場合には、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金刑となります。
3)ピンハネの禁止(労基法6条、118条)
会社は一部の法律(労働者派遣法など)で認められている場合を除き、労働者と雇用者の間に入って、利益を搾取してはいけません。これに違反した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
4)違約金の支払い約束や債権と賃金の相殺(労基法16条、119条)
すでに述べたとおり、労基法では賃金全額払いの原則があるため、従業員が違反行為をしても賃金と損害賠償金を相殺することは認められていません。これは、会社が従業員に貸し付けている貸金があった際の返還請求権の行使においても同様です。そして、これに違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。
5)予告なしの解雇(労基法20条、119条)
会社は従業員を解雇する際には、必ず1ヶ月前に解雇予告をするかあるいは、不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。これに違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。
6)36協定なしの時間外労働(労基法32条、119条)
会社は、時間外労働をさせる場合には、労働者との間で36協定を締結しなければなりません。これを締結せずに時間外労働をさせた場合には、労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。
7)休憩を与えない(労基法34条、119条)
会社は労働者に対して、6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には60分以上休憩を与えなければなりませんが、それを行わなかった場合には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。
8)休日を与えない(労基法35条、119条)
会社は労働者に対して、毎週1日の休日または4週間のうち4日以上の休日を与えなければなりませんが、これに違反した場合には、は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。
9)割増賃金の未払い(労基法37条、119条)
会社は労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合には、所定の割増賃金を支払わなければなりません。これに違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。
10)有給休暇の不支給(労基法39条、119条)
会社は労働者の勤務期間が半年以上となった場合には、有給休暇を付与しなければなりません。これに違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。
11)産前産後休暇・育児休暇の却下(労基法65条ないし67条、119条)
会社は、従業員から産休・育休の申請があった際には必ずこれを付与しなければなりません。これに違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。
12)就業規則の明示・作成・届出違反(労基法15条、89条、106条)
会社は従業員を雇い入れるにあたって、雇用条件を明示し、また10人以上従業員がいる事業所では就業規則を作成・届出をし、かつ労働者に周知させなければなりません。これに違反した場合には、30万円以下の罰金刑となります。
最後に
まだまだ、労働基準法に対する認識が甘い事業場が多く存在しています。労基法に、違反して刑事罰を受けることになってしまうと会社の損害は計り知れません。経済的な損害はもちろん、悪評がたってしまうことも十分に考えられるためです。
したがって、こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、企業としては研修等を積極的におこなって、管理者や現場のリーダーにしっかりと労働基準法を周知させていくことが非常に大切です。
また会社としてはこの労働基準法だけではなく、様々な労働法に関連する法律に目を配ることも必要となります。